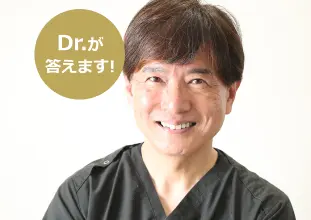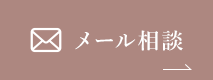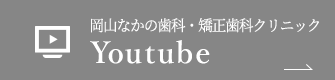ソウルSIDEX2025 バンコク インビザラインサミット
 ○韓国・ソウルSIDEX2025~インプラントとデジタルの標準化~
○韓国・ソウルSIDEX2025~インプラントとデジタルの標準化~
SIDEXは韓国最大規模の国際歯科展示会・学術大会で、今年も世界中から7万人以上が来場。会場には、最新のインプラントシステムや口腔内スキャナー、AI診断支援、デジタル歯科技工のソリューションなど、最先端の製品・技術が集結していました。
なかでも特に感じたのは、韓国がインプラント先進国として技術と制度の両面で一歩進んでいる現実です。精密な手術ガイドによるデジタルインプラント手術が標準化されており、国民健康保険の一部適用も後押しとなり、幅広い年代に治療が普及。「メガジェン」「オステム」など自国メーカーの勢いも圧巻で、材料供給やアフターサポートの強さが治療の広がりを支えています。
日本でもインプラント治療は浸透しつつありますが、普及率や診療フローのデジタル化は、まだ差があります。SIDEXの会場では「短期間で高精度の治療をいかに標準化するか」というテーマに各ブースが取り組んでおり、経営の効率化と患者満足度の両立に直結する視点を多く学びました。
○デジタルスキャナーが変える補綴と矯正の現場
韓国で特に印象深かったのは、口腔内スキャナーの普及率の高さです。従来のシリコン印象に代わり、スキャナーによる印象採得が「当たり前」となりつつあり、インプラント補綴だけでなくクラウン、義歯、矯正まで全面的にデジタル化が進行中です。
今回、最新機種を複数体験し、以下の特徴を実感しました。
- 超高速スキャンで患者負担を軽減
- リアルタイムの咬合データ取得
- スキャン直後にシミュレーション提示
- 3Dプリンターと連携し即日補綴物の製作が可能
韓国の若手歯科医師の多くは、こうしたデジタル技術を診療のベースに据えています。
「設備を導入するだけではなく、標準オペレーションに落とし込む仕組み」が成長の原動力だと感じました。
○タイ・バンコクのインビザラインサミット~完全デジタル矯正の未来~
SIDEXから帰国後、2日診療を行い、深夜便でタイ・バンコクへ移動。アジアパシフィック インビザラインサミットは、アジア・オセアニア地域の矯正歯科医師が集い、最新の治療技術や臨床データを共有する国際会議です。2年ごとにシンガポールで開催されることが多いこのサミットですが、今回初めて妻と参加。参加者は30〜40代が中心で、学会専用アプリを活用しながらディスカッションが進行するなど、運営も非常にデジタル化されていました。
本サミットのテーマの一つは、AIを活用した治療計画の進化。「ClinCheck Pro」を用いた治療設計支援や、アルゴリズムによる結果予測の精度向上は、臨床現場の生産性を大きく変える可能性を感じさせました。
また、マウスピース矯正の適応範囲が拡大していることも重要なポイントです。難症例や成長期の子どもに対する「インビザライン・ファースト」の臨床研究、インプラントや外科処置との連携治療(マルチディシプリナリーアプローチ)など、診療の幅が一層広がっていることを痛感しました。
○デジタル矯正が経営にもたらす影響
当院でもiTeroスキャナーを活用したデジタル矯正を本格導入していますが、今後はAIによるシミュレーションと診療支援が標準化され、患者さんの治療満足度や治療期間の短縮だけでなく、医院の収益性やオペレーション効率を大きく変える流れが加速するでしょう。今回、現地で参加されている方と交流する中では、治療技術だけではなく、次の点を経営者として再確認しました。
- デジタル機材を先行投資し、標準化することが中長期的な競争力になる
- 海外の治療手法を学び続け、地域に適応する柔軟性を持つこと
- スタッフ教育と運用フローの整備がデジタル投資の成否を決める
特にアジア圏では、若手ドクターほどデジタルを「当たり前のインフラ」として使いこなしています。彼らにならって、私たちの世代こそ、変化を恐れず学び直す覚悟が必要だと痛感しました。
○変化を恐れず、学び続ける
韓国・ソウルでは、SIDEX会場でメガジェンインプラントのブースを訪れた際、妻が「代表の方がいらっしゃるよ!」と教えてくれました。そこにはメガジェンインプラントのCEOであるP先生の姿がありました。P先生とは、数年前ブラジル・サンパウロのセミナーでご一緒し、同じテーブルで食事をしたご縁があります。私が挨拶させていただくと、P先生は大きな笑顔で「一緒に写真を撮りましょう!」と声を掛けてくださいました。
韓国を代表するインプラントメーカーの社長で、テグに大学病院並みの診療施設を構える方が、私のような一開業医にも気さくに声を掛けてくださる姿に、「実るほど頭が下がる稲穂かな」という言葉を思い出し、大変学びがありました。
バンコクでは、会場から離れたチャオプラヤー川沿いのホテルに滞在しましたが、移動は一筋縄ではいかず、片道20分の距離が1時間半かかることもしばしば。さらに6月のバンコクは強烈な蒸し暑さで、数分外に出るだけで汗が滝のようにあふれ、室内では冷房が効きすぎて薄手のスーツを後悔するほどでした。
サミット会場には30代を中心とした若手ドクターが集まり、学会専用のアプリを自在に使いこなし、活発にディスカッションを交わしていました。60代の私のような世代はほとんど見かけませんでしたが、そうした環境に身を置き、世代を超えて学ぶことこそ、これからの歯科医療に必要な姿勢だと改めて実感しました。幸い私は長距離移動に強く、体力的にも問題なく参加でき、「まだまだ現役で走れる」と再確認できたのも収穫です。
今回参加した2つの国際イベントは、いずれも「治療のデジタル化と標準化」がキーワードでした。これは技術の革新だけでなく、医院経営の質を高める挑戦でもあります。日本の地域医療においても、世界水準の治療を安心して受けられる環境を整えることは、患者さまの信頼と医院の未来を支える重要な投資です。
変化を恐れず、学び続ける。
これからもその姿勢を大切にしながら、地域の患者さま、歯科医療に携わる方々に還元してまいります。

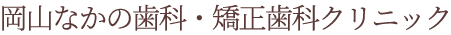


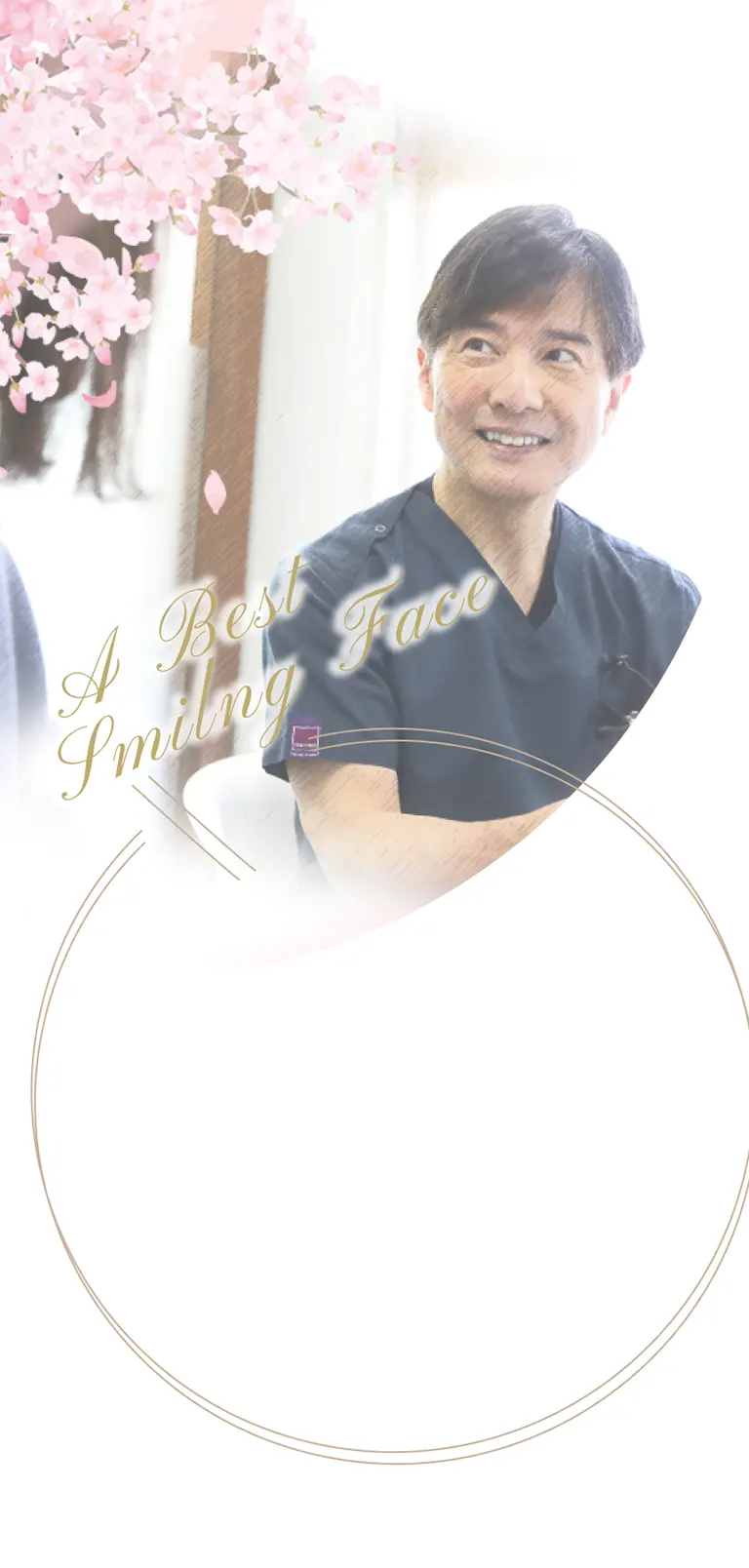



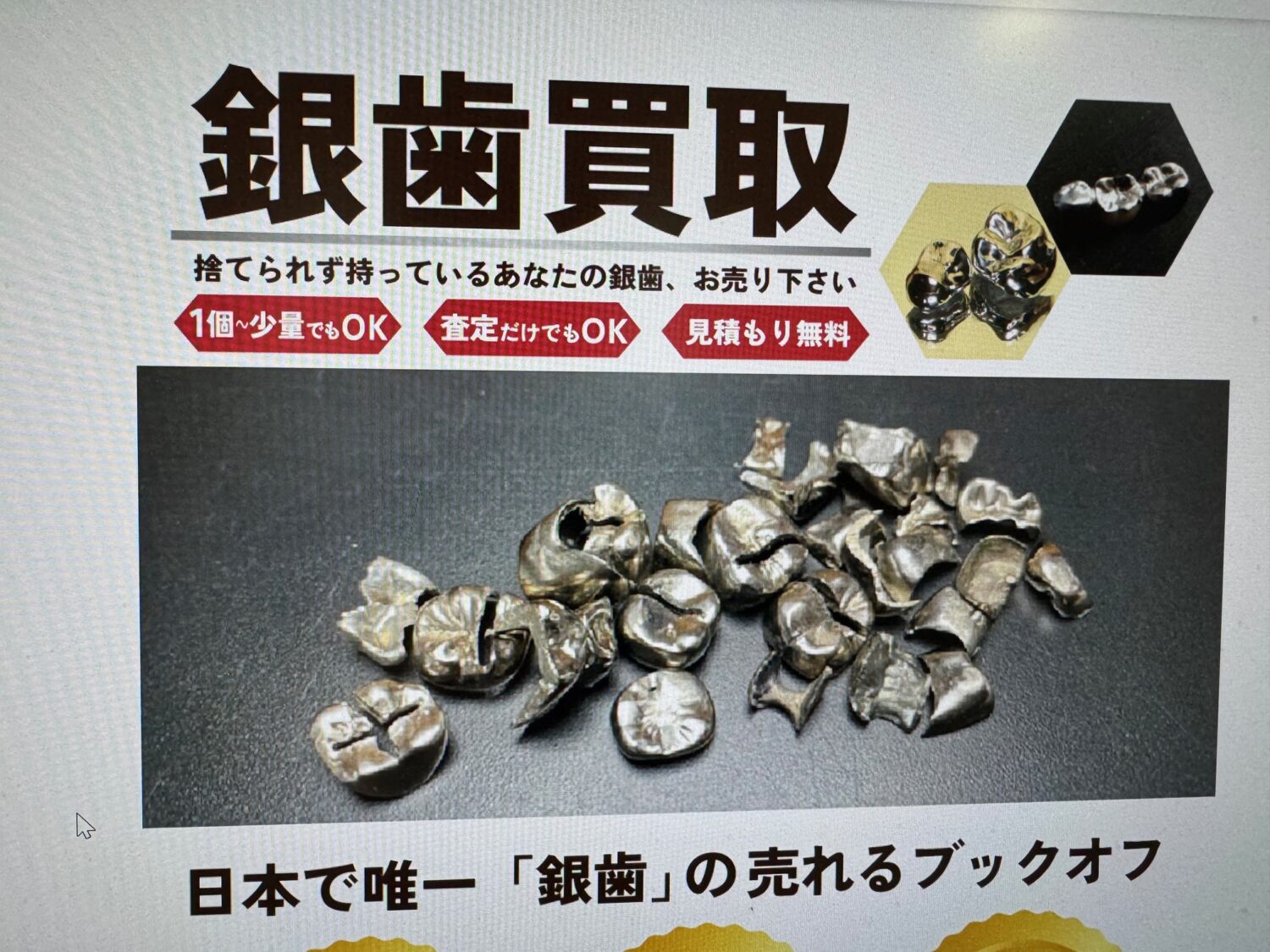



 Contact
Contact
 Line
Line